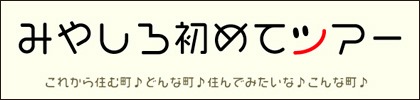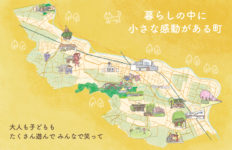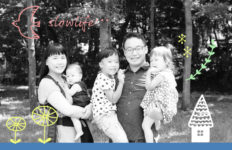松村 淳
陶芸家 宮代町出身
2018年Uターン
粘土をろくろでひき、乾いた状態の土を削っておおよその形を作り出し、素焼きをした後に「やすり」「削り」を繰り返して洗練されたシャープな形を生み出す。日本の現代工芸において期待の新進陶芸家として注目されている松村淳さんは笠原小学校の卒業生です。高校卒業後アメリカへ留学、帰国後多治見と金沢で陶芸の修行をされ、香港で活動後、宮代町に戻って来られました。
器の機能的突然変異を起こす

私はアメリカの大学で海洋生物学を専攻していました。海の生き物の生態を調べ進化の歴史を考察する。
そのロジックで「器」というものを考えた時に、器はその時代の生活環境によって形が変わり、
使われなくなったものは淘汰されていきます。「器も進化している」ならば、
器の系統樹の末端にいる自分が突然変異を起こしてもいいのではないかと思いました。
 |
 |
アメリカ生活で興味を持った日本文化
高校卒業後、語学留学を経て大学へ入学しました。そこでカルチャーショックを受け、
ホームシックになりました。日本が恋しくて、日本食を自炊するようになりました。
その時に盛り付けをする「器」に興味を持ちました。
それから興味を持って器を見るようになりましたが、
いわゆる「名器」とよばれる作品の良さが全くわかりませんでした。
 |
  |
いろいろな経験をして、多くの作品を知り、今は名器の良さがわかります。
それは瞬間の想いが高度な技術で凝縮されたもので、作ろうと思って作れるものではないのです。
それをなんとなく感じていたからでしょうか、アメリカにいた時は
器は好きでしたが、自分で作ってみようとは思いませんでした。
こういう器でもいいんだ

大学を卒業したのはリーマンショックの頃で、日本で就職活動をしましたが
なかなか決まらずカフェでバリスタのアルバイトをしていました。
アルバイト先にいろいろな器の雑誌があってそれを休憩時間によく眺めていました。
伝統的な陶芸は難しそうだと思っていたのですが
若い作家さんの作品でメタリックな釉薬を使ったものを見た時に
「こういう器でもいいんだ」と思ったのが陶芸をやってみようと思ったきっかけです。
磁器は気持ちが良い
就職活動を止め、陶芸を学ぶために多治見市陶磁器意匠研究所へ入りました。
そこで2年学び金沢卯辰山工芸工房で3年経験を積みました。
工房では作家としてブラッシュアップしながら
金沢の文化を学ぶために茶道、花道、書道等の稽古も受けました。
 |
  |
磁器の制作を選んだのは、触っていて気持ちがいいのと、
ろくろでの制作が難しく難易度が高いからです。私はその難しさに惹かれました。
また磁器は子どもの頃大好きでよく作っていたプラモデルのプラスチックの感じに
近いと思いました。私が刺激を受けたアニメやゲームや映画の
近未来の世界観が一番表現できるのが磁器だと思っています。
制作活動に適した環境
宮代町は私にとって制作に集中できる環境です。
都会へのアクセスが良いので、刺激(インプット)が必要な時は
電車で出かけて美術館を巡ったり人に会ったりします。
そして自分の制作と向き合う時(アウトプット)は
いい意味で静かなので、集中することができます。
町内の施設では図書館が好きでよく行きます。
開放的な空間で気持ちよく過ごすことができます。
朝ジョギングをする道にはいろいろな花が咲きます。
美しい花を見ながら季節の移り変わりを楽しんでいます。
小学校は刺激的でした

宮代町へは私が小学校に入学するのをきっかけに引っ越ししてきました。
両親は田舎暮らしに憧れていましたが、都内へ通勤していたので
交通の便がいい場所を探していたそうです。
母校の笠原小学校は、小学生にとってツッコミどころ満載の建物でした。
「なぜここにこれが?」という決して機能的ではない構造物があちこちにあって
その中に入ってみたりよじ登ったりして遊びました。
 |
  |
学校では裸足で過ごすので1階のあちこちに足を洗う場所があります。
でもそれ以外にも水場がいくつもありました。
中庭にある大きなじゃぶじゃぶ池や、流れた水が反対側へ伝って流れる手洗い場。
私にとってミステリアスな場所だったのは
なぜか2階にあった人工池でした。
開放的な校舎なので虫や鳥たちとの距離が近いし
木登りできる木があったり、今思うと楽しかったですね。

変わっていくこの町と一緒に
宮代町に戻って来た時に、昔より町全体が洗練されたなと感じました。
そして町内にはいろいろな方面のクリエイターがいることがわかってきました。
地元に長く住んでいる方もいれば移住されてきた方もいます。
そういう方たちとの交流の機会も持てるようになってきました。
私もこの町のクリエイターの一人として
陶芸の楽しさを多くの方に伝えていきたいので
自分の工房で陶芸教室を始めることにしました。
これから先も変わっていくであろうこの町と一緒に
私も成長したいと思います。

![]()
|
【編集後記】 松村さんの作品を初めて見たとき、謎めいた世界観に心が揺さぶられました。草木が萌えるようにも見え、宇宙へ突き抜ける硬質な船にも見え。もやもやを抱えたままご本人にお話しを伺って、宇宙のほうが正解でそれが松村さんが意図的に起こした突然変異だということで、若い感性は本当に面白いなと思いました。穏やかなお人柄の中に潜むいたずら心。茶道の茶碗も松村さんが手掛けるとこんなスタイルに! (よん)取材日 令和2年8月3日
|
<関連リンク>
TeTo LABO Studio / 「移住者インタビュー」バックナンバー / 「宮代暮らし」バックナンバー